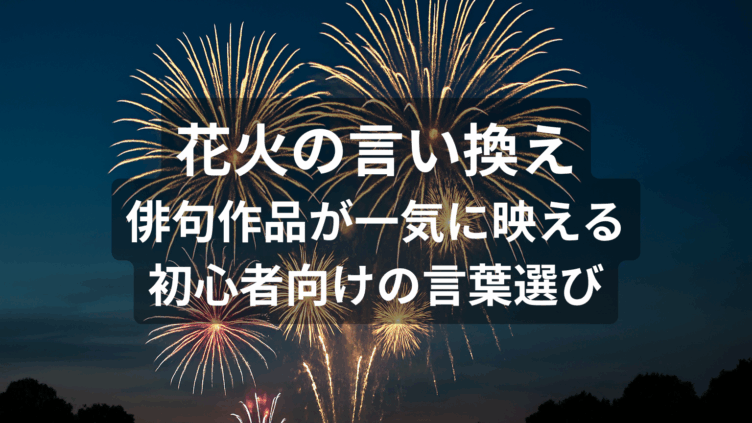 豆知識
豆知識 花火の言い換え|俳句作品が一気に映える初心者向けの言葉選び
俳句の「花火」を言い換えて作品をより魅力的に仕上げるコツを初心者向けに解説します。光や音をイメージした表現や使い分けのポイントをわかりやすく紹介します。
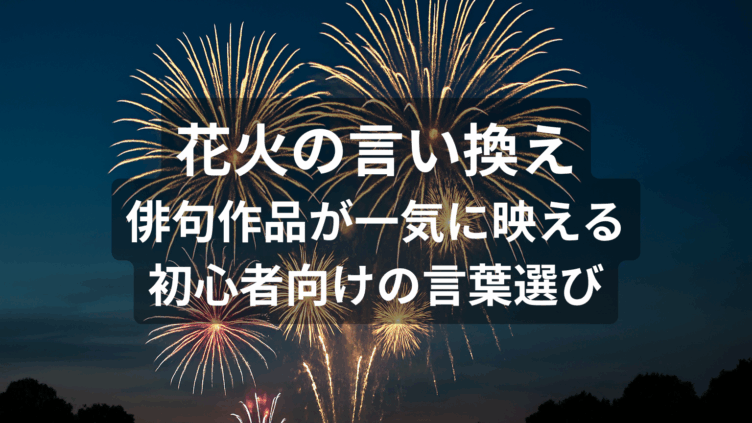 豆知識
豆知識 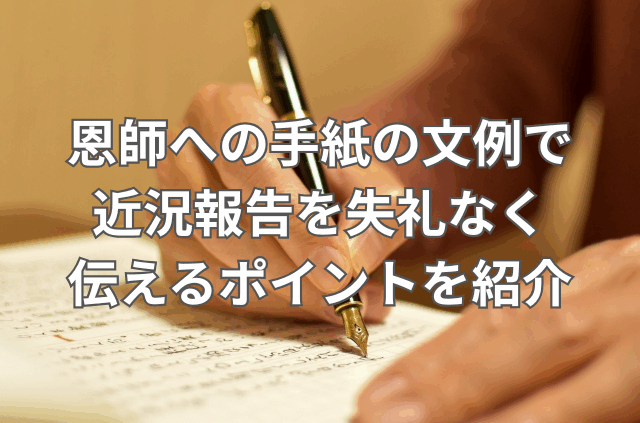 豆知識
豆知識  豆知識
豆知識 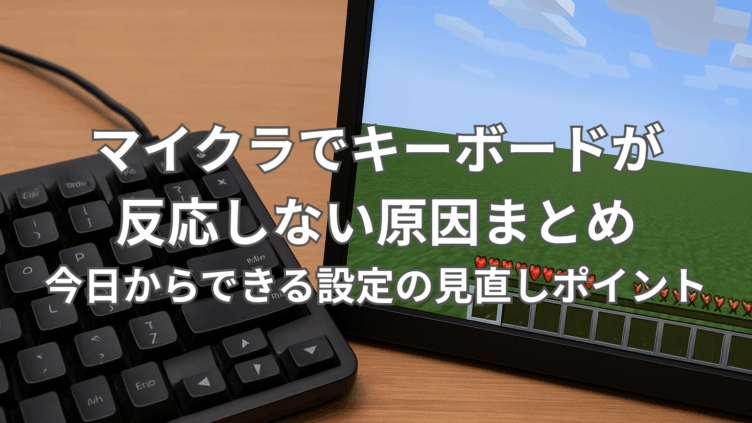 豆知識
豆知識  豆知識
豆知識 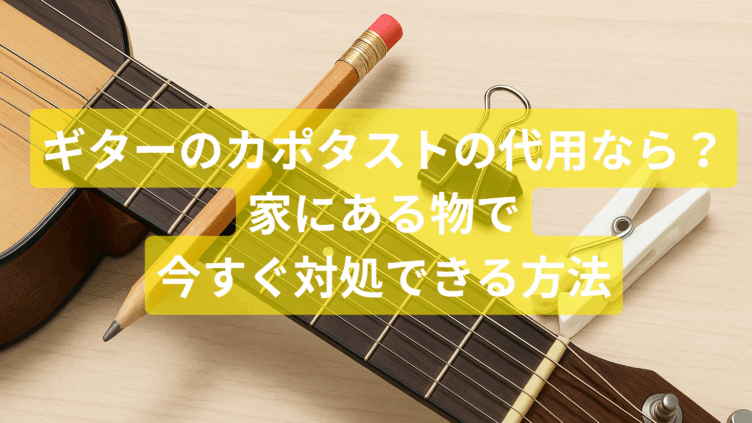 豆知識
豆知識  豆知識
豆知識 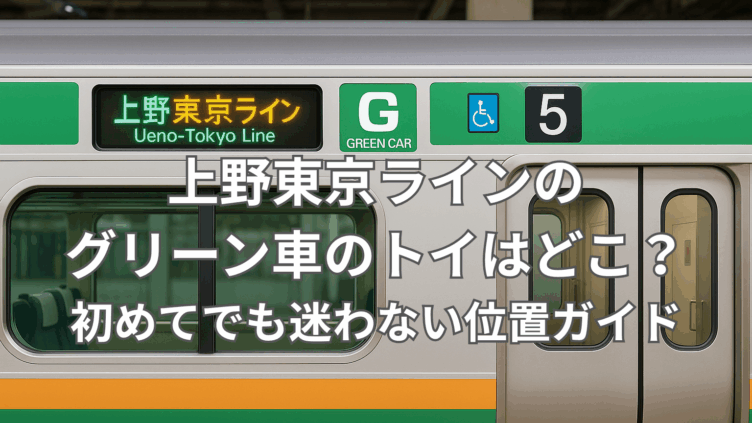 豆知識
豆知識  豆知識
豆知識  豆知識
豆知識