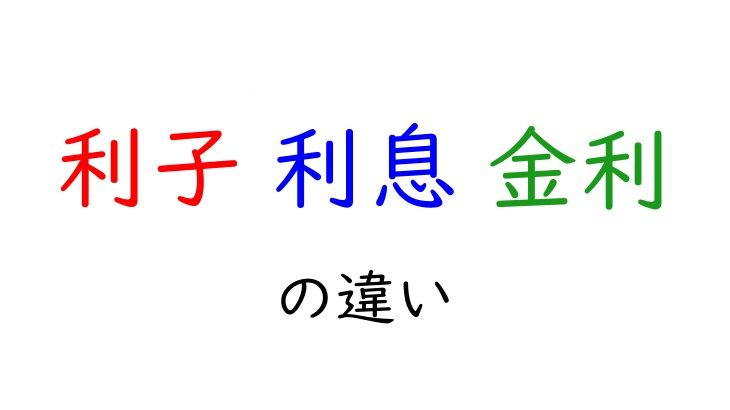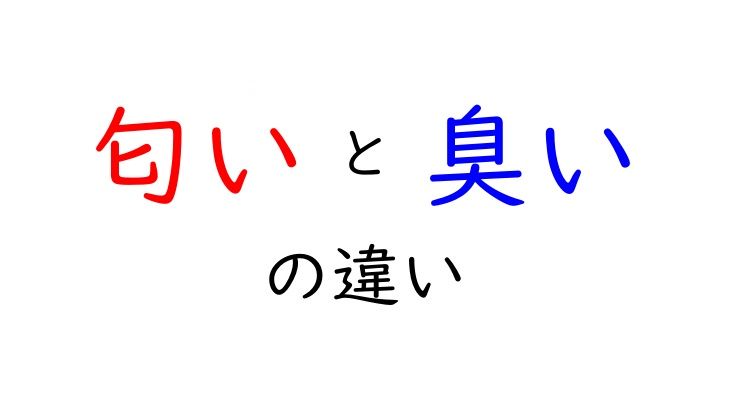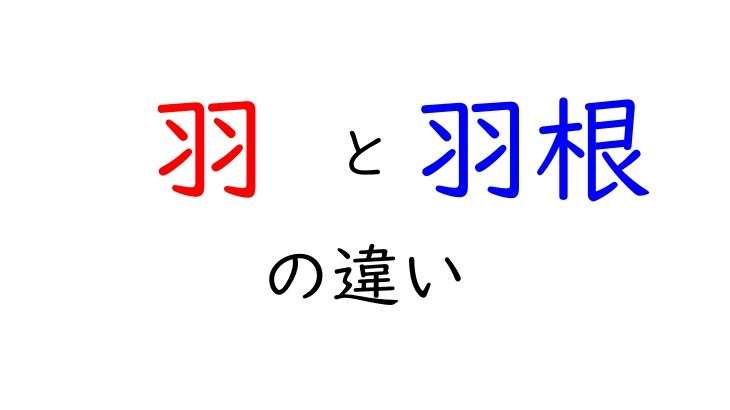利子、利息、金利――お金にまつわる言葉なのに、何がどう違うのか分からない…という方は多いのではないでしょうか?
貯金やローン、クレジットカードの説明でよく見かけるこの3つの用語。
似ているけれど、実はそれぞれに明確な意味と使い方があります。
結論から言えば、利子と利息は“お金そのもの”を表し、金利はその“割合”を示す言葉です。
言い換えると、利子や利息は「いくら受け取る(払う)か」、金利は「何%のペースか」といった違いがあります。
この記事では、初心者にもわかりやすい言葉で、利子・利息・金利の違いをざっくり解説していきます。
あわせて、それぞれの使い方や例も紹介するので、これを読めばもう混乱しません!
利子・利息・金利の違い
よく似た3つの言葉の基本的な関係
利子・利息・金利はすべて「お金を貸し借りすることで発生する利益やコスト」に関係した言葉です。
ただし、それぞれの視点や表す内容が少しずつ異なります。
結論:利子と利息は「お金のやり取り」、金利は「割合」
- 利子:お金を「預けた側」が受け取る利益
- 利息:お金を「借りた側」が支払うコスト
- 金利:利子や利息の「割合」(%)
つまり、利子と利息は“実際にやり取りされる金額”であり、金利はその「利子・利息がどのくらいの比率か」を示す数値です。
「利子」とは?お金を預けたときにもらえるもの
利子の意味と使い方
利子とは、お金を預けたことで得られる利益のことです。
たとえば銀行にお金を預けると、その銀行は預金を元手に融資などで運用し、その一部を「利子」として私たちに還元します。
銀行預金の利子の仕組み
普通預金や定期預金などに応じて金利が設定され、それに基づいて利子が毎年、あるいは数ヶ月ごとに付与されます。
金利が0.001%なら、100万円預けても年間10円しか増えませんが、それでも“預けるだけでもらえるお金”です。
日常生活での具体例
- 銀行の普通預金で年に数円〜数十円の利子がつく
- 定期預金やネット銀行ではやや高めの金利で利子が増える
「利息」とは?お金を借りたときに支払うもの
利息の意味と使い方
利息は、お金を借りた人が、貸してくれた人に支払う「借り賃」です。
住宅ローンやカードローン、クレジットカードの分割払いなどで「利息」が発生します。
ローンやクレジットで発生する利息
金融機関は、お金を貸してビジネスをしています。
借りたお金を返すときに、元本に加えて「利息」を上乗せして支払うのが一般的です。
例:30万円を年15%で借りた場合、1年後に支払う利息は45,000円になります。
利子と利息の違い
- 利子は“もらう”お金(預ける側)
- 利息は“払う”お金(借りる側)
このように、立場が違えば呼び方も変わるのがポイントです。
「金利」とは?利子や利息の“割合”を表す指標
金利の基本的な考え方
金利は、元本に対して何%の利子や利息がつくかを示す割合です。
年利や月利などの単位で表されることが多いです。
例:年利2%の場合、100万円を1年間預けると利子は2万円。
金利の種類(年利・実質年率など)
- 年利(年率):1年あたりの利率
- 実質年率:手数料なども含めた総合的な年利
- 変動金利・固定金利:金利が途中で変動するかどうか
特にローンを組む際には、表面上の金利だけでなく実質年率を見ることが大切です。
金利と利子・利息の関係性
金利が高ければ利子や利息の金額も大きくなります。
つまり、金利は利子・利息の元になる“計算式のカギ”です。
まとめ:利子・利息・金利の違いを簡単におさらい!
3つの言葉の使い分け早見表
| 用語 | 意味 | 誰が使う? |
|---|---|---|
| 利子 | 預けたお金に対する利益 | 銀行預金者など |
| 利息 | 借りたお金に対する支払い | ローンの利用者など |
| 金利 | 利子・利息の割合(%) | 金融商品を比較する人 |
日常で間違えないためのポイント
- 「預けて増える」なら利子
- 「借りて払う」なら利息
- それを決めるルールは金利
この違いをおさえておけば、預金やローンの選び方にも役立ちますし、お金の流れをしっかり把握できるようになります。