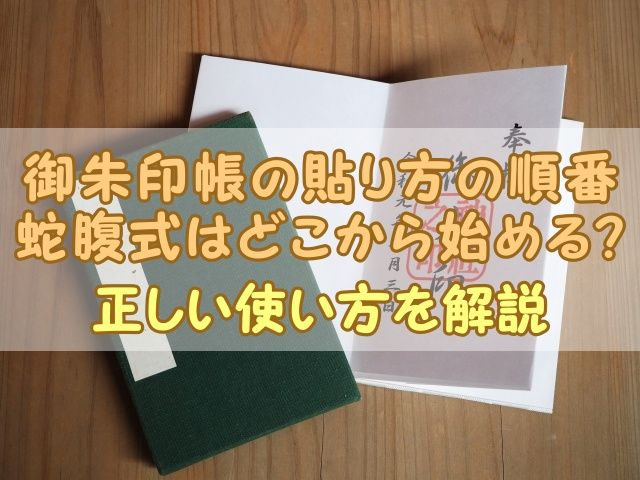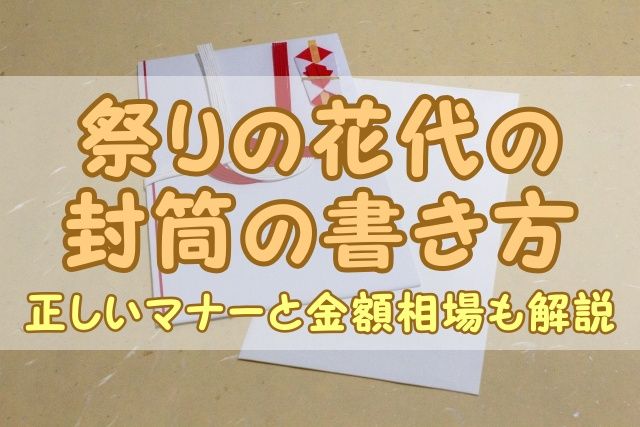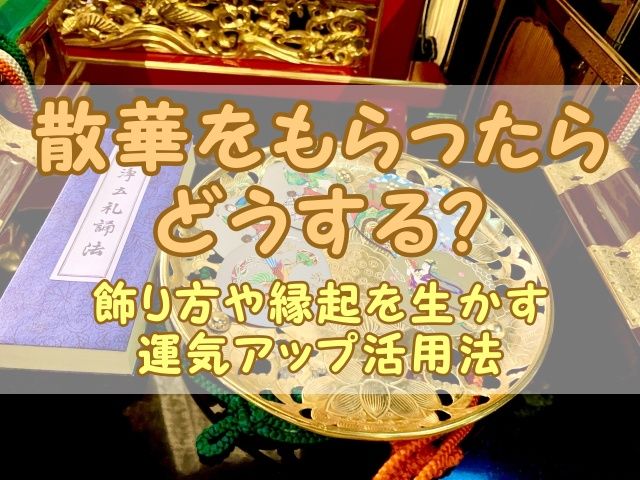神社やお寺を訪れたときにいただける御朱印は、旅の記念や信仰の証として人気があります。
近年では若い女性を中心に御朱印巡りがブームになり、旅行やおでかけの楽しみ方のひとつになっています。
しかし、初めて御朱印帳を持つと「御朱印帳のどのページから始めるの?」「蛇腹式ってどうやって使うの?」「御朱印を貼る順番に決まりはあるの?」と疑問に思うことも多いでしょう。
特に「書き置き御朱印」をいただいた場合、きれいに貼る方法やルールが気になる方が多いです。
この記事では、御朱印帳の基本から蛇腹式の特徴、御朱印の貼り方や順番、初心者が迷いやすいポイントまでをやさしく解説します。
基礎を理解しておけば、御朱印巡りをもっと安心して楽しめますよ。
御朱印帳の種類と蛇腹式のメリット
御朱印帳には主に「蛇腹式」と「和綴じ式」の2種類があります。
- 蛇腹式は紙がアコーディオンのように折りたたまれており、広げて見開きにできるのが特徴です。
書きやすく、裏写りもしにくいため、多くの人に選ばれています。 - 和綴じ式は本のように綴じられていて、コンパクトで持ち運びやすいメリットがあります。
ただし、裏写りしやすい紙もあるため、墨書きにはやや注意が必要です。
蛇腹式のメリットをまとめると以下のとおりです。
- 書き置き御朱印を貼りやすい
- 表面・裏面ともに使えて収納力が高い
- 墨がにじみにくい紙が多い
- 御朱印をいただく際に神職や僧侶が扱いやすい
デメリットを挙げるとすれば、折り目部分が使いにくい点や、広げると大きく場所を取る点ですが、初心者にとっては圧倒的に使いやすい形式です。
最近では可愛いデザインや地域限定の御朱印帳も増えており、選ぶ楽しさも広がっています。
御朱印を貼る順番|最初と最後のページの使い方
御朱印帳を使うときに一番迷いやすいのが「順番」や「最初のページをどうするか」という問題です。
順番に厳密なルールはある?
実は御朱印を貼る順番には厳密な決まりはありません。
基本的には「最初のページから順番に」貼れば問題ありませんが、旅の思い出として「訪れた順に貼る」方も多いです。
つまり、自分の思い出の残し方に合わせて順番を決めればOKです。
神社とお寺で分ける必要はある?
かつては神社とお寺を分ける考え方もありましたが、今では1冊にまとめても問題ありません。
ただし、気になる方は「神社用」「お寺用」と2冊用意するのもおすすめです。
- 1冊でまとめる → コンパクトで気軽に持ち歩ける
- 2冊に分ける → 神仏習合に抵抗がある人や整理したい人に向いている
自分のスタイルに合わせて選びましょう。
裏面を使っても大丈夫?
蛇腹式の御朱印帳は「表面から使う」のが一般的です。
ただし、裏面も墨が裏写りしないように加工されているものが多く、十分使用できます。
長く御朱印巡りを楽しみたい方は、裏面も活用して1冊を大切に使い御朱印を貼る順番|最初と最後のページの使い方
御朱印帳を使うときに一番迷いやすいのが「順番」や「最初のページをどうするか」という問題です。
順番に厳密なルールはある?
実は御朱印を貼る順番には厳密な決まりはありません。
基本的には「最初のページから順番に」貼れば問題ありませんが、旅の思い出として「訪れた順に貼る」方も多いです。
つまり、自分の思い出の残し方に合わせて順番を決めればOKです。
神社とお寺で分ける必要はある?
かつては神社とお寺を分ける考え方もありましたが、今では1冊にまとめても問題ありません。
ただし、気になる方は「神社用」「お寺用」と2冊用意するのもおすすめです。
- 1冊でまとめる → コンパクトで気軽に持ち歩ける
- 2冊に分ける → 神仏習合に抵抗がある人や整理したい人に向いている
自分のスタイルに合わせて選びましょう。
裏面を使っても大丈夫?
蛇腹式の御朱印帳は「表面から使う」のが一般的です。
ただし、裏面も墨が裏写りしないように加工されているものが多く、十分使用できます。
長く御朱印巡りを楽しみたい方は、裏面も活用して1冊を大切に使い
御朱印の貼り方|きれいに貼るためのコツ
御朱印には「御朱印帳に直接書いていただく」方法と、「書き置き御朱印を貼る」方法があります。
近年は人気の寺社では混雑を避けるために「書き置き」が増えているので、貼り方の基本を知っておくことが大切です。
必要な道具と準備
御朱印を貼る際には、以下の道具をそろえておくと便利です。
- スティックのり(紙が波打たないタイプがおすすめ)
- 両面テープ(のり跡が気になる方に)
- 定規(まっすぐ貼るために必須)
- ハサミやカッター(余白を整えるときに)
- 下敷き(貼るときに机を汚さないために)
作業の前に、机をきれいにして手を清潔にするのもポイントです。
墨がこすれると御朱印が台無しになってしまうので注意しましょう。
のりとテープどちらがいい?
御朱印を貼るときは「のり」と「両面テープ」の2種類が主流です。
- のり:紙全体に塗ると安定感があり、長期間でも剥がれにくい。スティックのりなら手が汚れにくく便利。
- 両面テープ:簡単に貼れるが、部分的にしか接着できないため角が浮きやすい。
長持ちさせたい場合は「のり」、手軽さを重視するなら「両面テープ」がおすすめです。
ただし、どちらを選んでも「薄く均一に塗る」「位置をしっかり合わせてから貼る」ことが大切です。御朱印の貼り方|きれいに貼るためのコツ
御朱印には「御朱印帳に直接書いていただく」方法と、「書き置き御朱印を貼る」方法があります。
近年は人気の寺社では混雑を避けるために「書き置き」が増えているので、貼り方の基本を知っておくことが大切です。
御朱印帳で初心者がやりがちな失敗と注意点
御朱印帳を使い始めた初心者がついやってしまう失敗をまとめました。
- のりを塗りすぎて御朱印がシワになる
- ページの上下を逆に貼ってしまう
- 日付や場所を記録せず、後でどこの御朱印かわからなくなる
- 折り目部分に貼ってしまい、きれいに閉じられなくなる
これを防ぐためにできることは以下のとおりです。
- のりは薄く均一に塗る
- 貼る前にページの上下を確認する
- 日付や寺社名を小さく書き添えておく
- 貼る位置を定規で軽く測ってから作業する
少し手間をかけるだけで、仕上がりが格段にきれいになります。
御朱印帳を長持ちさせる保管方法と持ち歩きの工夫
せっかく集めた御朱印帳は、長く大切に使いたいものです。
保管方法
- カバーをつける:布製やビニール製のカバーを使うと汚れや摩耗を防げます。
- 直射日光を避ける:日光で紙や墨が劣化するので、暗い場所で保管すると安心です。
- 湿気に注意:湿気は紙の大敵。除湿剤と一緒に保管すると長持ちします。
持ち歩きの工夫
- バッグの中で折れないよう、専用ケースやポーチに入れる
- 雨の日はビニール袋で保護する
- ページが勝手に開かないよう、ゴムバンドで軽く留める
こうした工夫をすることで、御朱印帳をきれいな状態で保つことができます。
御朱印帳の貼り方の順番 まとめ
御朱印帳の貼り方や順番には、実は厳密なルールはありません。
蛇腹式は初心者でも扱いやすく、御朱印をきれいに整理できるため人気があります。
御朱印を貼るときは「のり」や「両面テープ」を使ってシワやズレに注意しましょう。
順番は基本的に最初のページから使えば問題ありませんが、自分の旅の記録として自由に貼って大丈夫です。
神社とお寺を分けるかどうかも、自分のスタイルに合わせて選べばよいでしょう。
大切なのは「自分だけの御朱印帳を育てる」ことです。
保管や持ち歩きの工夫も取り入れて、思い出の詰まった一冊に仕上げていきましょう。