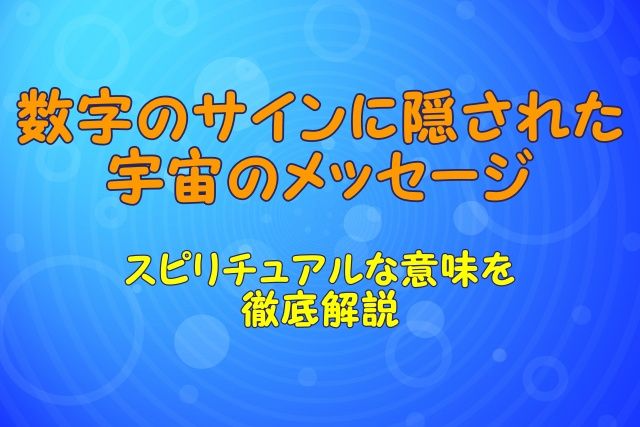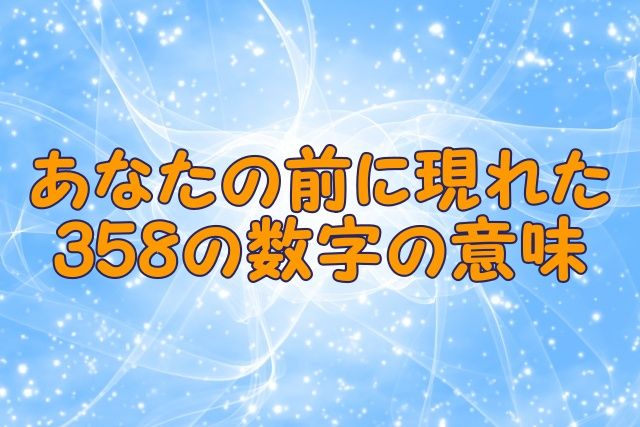数を数えるだけなのに、なぜこんなに面白い?
日本語の数え方や単位には、私たちが普段気づかない驚きと歴史が隠れています。
この記事では、そんな珍しい数え方を一挙に紹介!
知れば思わず誰かに話したくなる、奥深い日本語の世界へご案内します。
日本語の奥深さ!数え方・単位の基礎知識
そもそも数え方と単位って何?
日本語には、モノを数えるときにその形や性質に合わせた「数え方」や「単位」があります。
たとえば、「一匹の犬」「一枚の紙」「一本の鉛筆」など、同じ「1つ」でも言い方が変わります。
これは、モノの特徴を言葉で表そうとする日本人の細やかな感性の表れともいえます。
単位とは、この数え方で使う「匹」「枚」「本」といった言葉のことです。
英語で言えば「a piece of paper」の「piece」にあたる部分です。
日本語の数え方は、物の形、大きさ、用途、さらには生きているかどうかでも変わります。
このため、日本語を学ぶ外国人にはとても難しい部分ともいわれています。
でも、この数え方の違いを知ることで、日本語の面白さや奥深さに触れることができるのです
日常で当たり前のように使っている数え方も、意識してみると新しい発見がたくさんあります。
この記事では、そんな珍しい数え方や単位を、歴史や由来とともに楽しく学んでいきます。
動物の数え方の基本ルール
動物を数えるとき、日本語ではその大きさや種類によって使う単位が違います。
小さな動物は「匹」、大きな動物は「頭(とう)」で数えることが多いです。
たとえば、犬や猫、ネズミは「匹」。牛や馬、ゾウのような大きな動物は「頭」と数えます。
ただ、これは厳密に決まっているわけではなく、地域や時代によって少しずつ違うこともあります。
漁師さんの世界では、魚を「匹」で数えたり「尾(び)」で数えたりします。
また、鳥は一般的に「羽(わ)」と数えますが、ウサギも昔は「羽」で数えた歴史があります。
これは宗教や文化的な理由が関係しているのです。
動物の数え方は、日本人が自然とどんなふうに向き合ってきたかを知る手がかりにもなります。
この基本ルールを知ると、珍しい数え方の面白さがより深く理解できるでしょう。
モノによる数え方の違いとは?
モノの数え方もまた、形や用途によって変わります。
例えば、紙は「枚」、鉛筆は「本」、机や椅子は「脚(きゃく)」や「台」で数えます。
傘や刀のような細長いモノも「本」です。
一方で、平らなモノや薄いモノは「枚」で数えるのが基本です。
お皿やCD、切符も「枚」です。
さらに、一見同じような形に見えるモノでも、使い方や伝統的な理由で数え方が違うこともあります。
たとえば、畳は「枚」ではなく「畳(じょう)」という単位で数えますよね。
これは、畳が部屋の広さを示す単位としても使われるからです。
このように、モノの数え方には日本人の暮らしや文化が色濃く反映されています。
普段何気なく使っている数え方ですが、その違いに目を向けると、とても興味深い世界が広がっています。
単位の由来を知ると面白い理由
数え方の単位には、昔の人の知恵や生活が詰まっています。
たとえば、「升(ます)」という単位は、もともと米や酒の量をはかる木の箱の名前でした。
その箱1つ分の量を「一升」と呼んだのです。
また、「匹」は、布を一反(たん)に切るときにできる端の部分を「匹」と呼んだのが始まりで、のちに小さな動物を数える単位になったと言われます。
単位の由来を知ると、単なる数のルール以上に、日本人のものづくりや暮らしぶりが見えてきます。
そして、なぜこのモノがこの単位で数えられるのかという疑問が解けると、もっと日本語の数え方が面白く感じられるでしょう。
学校ではあまり詳しく習わない内容ですが、知っておくと話のタネになること間違いなしです。
数え方と文化の関係性
日本の数え方は、そのまま文化や歴史と深く結びついています。
たとえば、ウサギを「羽」で数えるのは、仏教で四足の動物を食べるのが禁じられていたため、鳥と同じように扱うことで食べることを正当化した名残です。
また、「升」や「斗」「石」などの単位は、米や酒など暮らしの基盤となるものを計るために生まれました。
こうした単位は今も神社の祭りや伝統行事などで使われています。
このように、数え方の背景を知ることで、日本文化の成り立ちや先人の知恵に触れることができます。
普段は気にしない数え方ですが、その奥には深い歴史と文化が息づいているのです。
珍しい動物の数え方ってどんなの?

ウサギは「羽」で数える理由
ウサギを「羽」で数えるのは、日本独自の文化や宗教的な背景が関係しています。
昔の日本では、仏教の影響で四足の獣を食べることが禁じられていました。
ですが、食生活の中で動物性のタンパク質はどうしても必要です。
そこで、ウサギを鳥の仲間として扱い、「羽」で数えることで食べても良いものとしたのです。
もちろんウサギには羽はありません。
でも、その数え方だけで鳥と同じ扱いにしたのです。
今では日常でウサギを数える機会は少なくなりましたが、昔の人の知恵や工夫が生んだ日本語の面白い一面といえます。
さらに、ウサギが「羽」で数えられることを知っていると、ちょっとした会話のネタや雑学としても役立ちます。
日本語の数え方の奥深さと、文化のつながりを感じられる例ですね。
カラスは「羽」じゃなく「羽(わ)」の謎
カラスを数えるときは「羽(わ)」という単位を使いますが、実はこの「羽」は鳥の羽根そのものを意味するものではなく、鳥一羽そのものを表します。
ですから、カラスに限らずスズメやハトなど多くの鳥は「一羽(いちわ)」と数えます。
それではなぜ「羽」と書くのに「羽(はね)」とは読まないのでしょうか。
これは、古くからの日本語の読み方がそのまま残っているからです。
「羽(はね)」は羽そのもの、「羽(わ)」は鳥の数を表す読み方なのです。
カラスは特に神話や昔話でも特別な存在として語られることが多く、八咫烏(やたがらす)などの神聖な鳥としても知られています。
こうした背景もあって、数え方の言葉が古い形のまま受け継がれてきたのかもしれません。
牛や馬の「頭(とう)」の由来
牛や馬のような大きな動物は「頭(とう)」で数えます。
これは、家畜として人と深く関わってきた歴史が理由です。
昔の農家や牧場では、家畜の管理のために頭数を数える必要がありました。
そのため、一頭、二頭と数えて、どのくらいの家畜がいるかを把握していたのです。
英語の「head of cattle(家畜の頭数)」と同じように、世界中で家畜の数を頭で表す文化が見られます。
また、牛や馬は大きくて力のある動物なので、「匹」ではなくより特別な数え方が必要だったともいわれています。
現代でも、競馬や牧場で「頭」で数える習慣は残っています。
この数え方の背景には、人と動物の密接な暮らしが見えてきますね。
蛇は「匹」?「条」?正しい数え方
蛇を数えるとき、多くの人は「匹」を使うことが多いですが、実は正式には「条(じょう)」という単位が使われます。
「条」は細長いモノを数えるときに使う単位で、蛇の他にも川や道、縄などに使われます。
蛇のように細長い体を持つ生き物には「条」という数え方がぴったりだったわけです。
とはいえ、現代ではあまり「条」を使う場面は少なく、「匹」で代用されることが多くなっています。
でも、古い文献や伝統行事では「条」が使われていることもあり、この数え方を知っていると日本語の奥深さを感じることができます。
蛇を見かける機会は少ないかもしれませんが、知識として知っておくと面白いですよ。
昆虫の意外な数え方とその背景
昆虫は一般的に「匹」で数えますが、種類によっては「頭」や「羽」を使うこともあります。
たとえば、特別に大きな昆虫や神聖視される昆虫(カブトムシやクワガタなど)は、子どもたちの間で「頭」で数えることもあります。
また、昔の農村では、害虫駆除の報告で数えるときに「匹」ではなく「頭」として数を報告したこともあったといいます。
さらに、トンボや蝶のように美しい羽を持つ昆虫は「羽」で数えたという記録も残っています。
昆虫の数え方一つ取っても、地域や時代、使う人の立場によってさまざまな数え方があったのです。
こうした柔軟さも、日本語の魅力のひとつといえるでしょう。
日常であまり聞かないモノの単位

のりは「帖」で数える!その理由
のり(海苔)を数えるとき、「枚」ではなく「帖(じょう)」という単位が使われます。
この「帖」というのは、紙や薄いものを何枚かまとめた束を意味する言葉です。
のりは昔、紙と同じように板状に乾かして作られていたため、和紙と同じように「帖」でまとめて数えるのが一般的だったのです。
たとえば、「一帖のり」といえば、10枚や100枚といったまとまった単位のことを指します。
今ではあまり耳にしない数え方ですが、のりが贈答品として高価だった時代には、「帖」で数えるのが当たり前でした。
寿司屋さんなど、のりの質にこだわる専門の職人さんたちの間では、今も「帖」という単位が使われることがあります。
日常ではなかなか聞かないですが、知っていると和食文化の奥深さを感じられる豆知識です。
屏風の「曲(きょく)」って何?
屏風(びょうぶ)を数える単位は「曲(きょく)」です。
屏風は折りたたみ式で、いくつかのパネルが連なってできています。
この連なった部分、つまり一折れ分を「一曲」と数えるのです。
屏風自体を数えるときは「一双(そう)」という数え方を使うこともあります。
「双」は左右一対の意味で、左右に置く2つ1組の屏風を表します。
屏風はもともと、風を防いだり空間を仕切ったりする道具で、部屋の中を美しく見せる役割も果たしていました。
そのため、数え方にも格式や美意識が込められているのです。
現代では屏風を使う機会は少ないですが、美術館や神社仏閣で見かけたとき、この「曲」や「双」という数え方を知っていると、ぐっと教養を感じさせるポイントになりますよ。
着物の「反(たん)」の意味
着物の生地を数えるときに使う「反(たん)」という単位。
これは着物一着を仕立てるのに必要な布の長さを表します。
おおよそ12メートル前後の反物(たんもの)1本分が「一反」です。
昔は反物を買って、自分の体に合わせて仕立てるのが当たり前だったため、「反」という単位が広く使われていました。
着物文化が日常から離れた今では耳にする機会が減りましたが、呉服屋さんや和装業界では今も使われています。
また、反物は着物以外にも暖簾や帯などの材料にもなります。
「反」という単位を知っていると、和の文化や伝統工芸の話題で役立つこと間違いなしです。
日本の織物文化の奥深さが感じられる単位のひとつです。
雨や雪の量の昔の単位とは
今では雨や雪の量は「ミリメートル」で表しますが、昔の日本には独自の単位がありました。
たとえば「寸(すん)」や「尺(しゃく)」を使って積雪や雨量を測っていたのです。
1寸はおおよそ3センチ、1尺は約30センチです。農業が生活の中心だった時代、雨や雪の量は作物の出来を左右する大切な情報であり、細かく記録されていました。
寺社の記録や古文書には、「今年は積雪三尺に及ぶ」などと記されています。
こうした単位は、日本人が自然と密接に暮らし、四季の変化に敏感だったことを物語っています。
現代では見かけることの少ない単位ですが、昔の気象記録や歴史資料に触れるときに知っておくととても役立ちます。
紙の「枚」と「葉」の違い
紙を数えるとき、「枚」と「葉」という2つの単位があります。
普段私たちは「枚」を使うことが多いですが、昔は「葉」もよく使われていました。
「葉」は、もともと木の葉のように薄いものを数える単位で、紙のほかに板や札などにも使われていました。
「枚」はその後、広く薄いものを数える単位として使われるようになり、「葉」より一般的になったのです。
現在、「葉」という単位は書物や古文書の世界で見かけることが多いです。
たとえば「一葉目」といえば、一番目の紙、つまり一枚目のことです。
こうした言葉の違いを知っておくと、日本語の表現の豊かさに気づくことができます。
日常生活では「枚」で十分ですが、歴史や文化を感じたいときには「葉」という言葉も意識してみると面白いですよ。
江戸時代から残る珍しい数え方

お金の単位「両」「文」「貫」
江戸時代のお金の単位といえば、「両」「文」「貫」があります。
「両」は金貨の単位で、「文」は小銭、「貫」は小銭をまとめた単位です。
1貫は約1000文に相当します。
当時、日用品は文、ぜいたく品や大きな取引は両で値段を表すことが一般的でした。
これらの単位は、日本独自の貨幣制度と暮らしの様子を今に伝えるものです。
時代劇や歴史小説で「三両の賞金」などと出てきますが、これは今の感覚でいえば数十万円から百万円以上の価値があったとされています。
このように、お金の数え方ひとつにも、その時代の生活感覚や経済の仕組みが表れているのです。
米や酒の「升」「斗」「石」
米や酒を量るときに使われた「升」「斗」「石」という単位は、農業国だった日本を象徴するものです。
1升は約1.8リットル、10升で1斗、10斗で1石です。
「石」は特に米の生産量を表すのに使われ、1石は成人男子が1年で食べる米の量とされていました。
江戸時代の武士の禄高(給与)も「石」で表され、「三百石取りの侍」などと表現されました。
これらの単位は今も酒造りや米の取引で名残をとどめています。
単位の背後に、日本の米文化の重要さが垣間見えますね。
布の「疋(ひき)」とその歴史
布を数えるときの単位として「疋(ひき)」という言葉があります。
現代ではあまり耳にしませんが、昔は布や反物を数えるときに広く使われていました。
「一疋」は、おおよそ一反の布の長さに相当し、12メートルほどの長さを意味します。
布は貴重な財産だったため、正確に長さを数える必要があり、こうした単位が生まれたのです。
また、布だけでなく、糸や織物などの取引にも「疋」が使われていました。
「疋」という字は、もともと「匹」と同じ意味を持っており、布や糸を1まとまりとして数えるときに使われたのが始まりとされています。
時代とともに布の数え方は「反」に移り、「疋」はあまり使われなくなりましたが、古文書や古い商家の記録などでは今も見ることができます。
こうした単位を知ることで、昔の商売や暮らしの姿がより身近に感じられます。
船の「艘(そう)」の数え方のルーツ
船を数えるときに使う単位が「艘(そう)」です。
この「艘」は船の数を表す古くからの数え方で、大きさや用途に関係なく船全般に使われます。
たとえば「一艘の舟」といえば、一隻の舟のことです。
英語でいう「ship」や「boat」のように、船を数えるときの一般的な単位です。
では、なぜ「艘」という字が使われるようになったのでしょうか?
これは、もともと中国から伝わった言葉で、船のように水に浮かぶものを表す漢字です。
日本でも古代から港町や漁村などで広く使われ、江戸時代には漁船や商船を数えるときの標準的な単位となりました。
今でも漁業や港の仕事では「艘」が使われています。
船の数え方の背景には、日本の海との深い関わりが見えてきます。
火事の被害の数え方の不思議
江戸時代、火事の被害を表すときには「町」「軒」「間(けん)」という単位が使われました。
「町」は町内単位の被害の広さ、「軒」は焼けた家の数、「間」は建物の幅を表していました。
火事の多かった江戸では、どれだけ被害が広がったのかを正確に伝えるために、こうした単位が必要だったのです。
「本町三町焼失」「百軒焼け落ち」などと記録され、火消しの手柄や再建の目安にもなりました。
現代ではこうした数え方を耳にすることはほとんどありませんが、古い記録や時代小説を読むときに覚えておくと便利です。
この数え方を知ると、江戸の町がどれだけ火事と隣り合わせで暮らしていたかがよくわかります。
話のネタに!日本独自の面白い単位
武士の「人」じゃなく「騎」で数える理由
戦国時代や江戸時代の武士を数えるとき、特に騎馬武者の場合は「騎(き)」という単位が使われました。
「一騎」とは、馬に乗った武士1人とその馬1頭を合わせた数え方です。
これは馬と武士が一体となって戦う存在だったことを表しています。
たとえば「一騎当千」という言葉は、ひとりで千人の敵に匹敵するほどの強さを持つ武士を称える言葉です。
歩兵は「人」で数え、騎馬武士は「騎」で数えることで、戦の記録や武功の評価に違いをつけていたのです。
この数え方は、日本の武士文化の象徴ともいえるでしょう。
絵巻物の「巻」の意味
絵巻物は「巻(かん)」という単位で数えます。
「一巻」とは、絵や文字が描かれた一つの巻物全体を指します。
絵巻物は巻いて保管するのが一般的であったため、この数え方が定着しました。
「源氏物語絵巻」や「鳥獣戯画」などの有名な絵巻物も「巻」で数えられます。
絵巻物は古来、物語や歴史、風景などを美しい絵と文字で表現する貴重な文化財でした。
数え方の中に、日本の美意識や記録の工夫が感じられます。
書物の「冊」と「部」の違い
書物を数えるとき、「冊」と「部」という2つの単位があります。
「冊」は一冊ごとの本を数えるときに使い、「部」は一組の本、つまりシリーズや全巻セットを指すときに使われます。
たとえば、「全5冊で1部の全集」といった具合です。
この違いを知っていると、図書館や書店での表記の意味がよくわかります。
日本の書物文化の細やかさを感じられる数え方です。
塩の「塊(かい)」という古い単位
塩は昔、「塊(かい)」という単位で数えられていました。
「一塊」は、塩を固めたかたまり一つを意味します。
塩は保存や運搬のため、石のように固められて取引されていたためです。
現代では「キロ」や「グラム」で測りますが、昔はこのように形や状態に合わせた数え方が使われていたのです。
塩の数え方ひとつにも、昔の人々の知恵や暮らしぶりが見えてきます。
宝石の「粒」と「顆」の違い
宝石を数えるとき、「粒」は今もよく使われますが、昔は「顆(か)」という単位も使われていました。
「粒」は小さな丸いもの全般に使う単位で、「顆」は特に玉状のものを美しく表現する言葉でした。
真珠や珊瑚などの高価な宝石には「顆」が使われ、宝飾品の格を表す役割もありました。
こうした数え方を知ることで、宝石の価値や扱いの違いを理解することができます。
その他のユニークな数え方一覧

以下では、その他の珍しい数え方を簡単に紹介します。
- 丁(ちょう)
豆腐やこんにゃくなどの四角い塊を数えるときの単位。 - 腹(はら)
魚の切り身や、特に大きな魚の身を一腹ずつに分けたときの単位。 - 杯(はい)
丸ごとのイカを指す単位で、体の形が器(杯)に似ていることに由来。 - 貫(かん)
寿司屋でネタとシャリのセット1つを数える単位。 - 握(あく)
昔の言い方で、手で握ったご飯一つを数える単位。 - 束(たば)、把(ぱ)
乾麺を数えるときの単位。「把」は古い表現です。 - 玉(たま)
特に丸い果物は「玉」とも数えます。農家や市場では「玉」を使うことが多いです。 - 層(そう)
塔や仏塔の階層を数える単位。 - 口(くち)
井戸や泉の数え方。 - 振(ふり)
刀剣の数え方。 - 躯(く)
仏像の数え方。 - 座(ざ)
山や大きな岩を数える単位。 - 宇(う)
寺院や神社の建物を数える単位。 - 基(き)
石灯籠や墓石を数える単位。 - 張(ちょう)
太鼓や弓の数え方。 - 面(めん)
琴や箏など平たい楽器を数える単位。 - 帖(じょう)
敷物や絨毯を数える単位。 - 挺(ちょう)
櫛を数える単位。 - 扇(せん)
扇子を数える単位。
まとめ
日本語の数え方や単位には、モノや動物の形、用途、文化、歴史が色濃く反映されています。
日常では当たり前に使っている「匹」や「枚」から、あまり耳にしない「帖」や「疋」、「顆」など、奥深くユニークなものまでさまざまです。
それぞれの数え方には、昔の人の暮らしぶりや知恵、価値観が詰まっています。
これらの数え方を知ることで、日本語の面白さや日本文化の奥行きを感じることができます。
ぜひ、身近なモノを数えるときに少しだけ意識してみてください。
それだけで、普段の生活がちょっと楽しく、豊かになるかもしれません。